いつも通りに僕は屋上に出た。
毎日毎日同じ事の繰り返しの学校。そんな日々を唾棄しながらも僕はそれに反抗することも無く、従順にその中に組み込まれていた。そして、自分の中のちっぽけな自尊心を満足させるために、毎日放課後、屋上に上り町を見下ろしていた。
今の僕は本当の僕じゃない。こんな画一的な教育システムの中では僕は、僕の本当の才能を、能力を、チカラを発揮することはできないのだ。僕はこんなくだらない奴等の中にいるべき人間じゃないんだ。僕はそう確信していた。
そして僕は孤高の中にいる。
教室でも誰も僕に話し掛けてくる奴はいない。
それでいいのだ。
僕より劣るこんな奴等と話したとして何が得られるというのだ。こんな奴等と僕に、何の関係があるというのだ。こんな奴等とこんな奴等と、こんな奴等と……。
「長瀬君!」
「え?」
「長瀬君、何度呼んだら気が付くのよ!」
女の子の声に、ふ、と僕は僕の世界から呼び覚まされた。
顔を上げるとそこには怒った顔のおかっぱの少女がいた。見覚えのある顔、、、でも名前は思い出せない。いきなり話し掛けられ、僕はドキマギとしてしまった。
「あ、あの、、何?」
「はい、これ週番日記。長瀬君、今週から週番なんだからちゃんとやってよね」
「週番?」
「そう! 昨日長瀬君、放課後すぐ居なくなっちゃったじゃない。あたし一人で週番のお仕事したんだから」
「あ、そう、、、」
「『あ、そう』じゃないの! もう、今日は逃げないでちゃんと週番のお仕事してね!」
女の子はひとしきり怒ると僕に週番日記を押し付けて、僕の机から去っていった。
(なんか、長瀬君ってへんー)
遠くからそんなささやきと僕へ向けられた女の子達の冷ややかな笑い声が聞こえてきた。そして血が逆流して耳が熱くなり、頭の中が真っ白になっていった。
そしてまた今日も、放課後僕は屋上へと上ってゆく。
ここに来て校庭を見下ろす。
同じように笑い、同じように騒ぐ、くだらない奴等を見下ろす。テレビや雑誌から垂れ流される事を何も考えずに喜んで口を開けて飲み込む奴等。自分で考える事の出来ない、そして、そういう奴等が作ったモノ、この街をここに来て見下ろす。
僕は違う。
奴等とは違う。
誰か一人がジルバを踊りだせば、他の奴等も一緒にジルバを踊り出すだろう。
でも奴等が馬鹿みたいにジルバを踊ったって僕は踊らない。
女の子は僕を見て笑う。
それは本当の僕を知らないからだ。僕の本当のチカラをしらないからだ。僕の本当の力を知ればあいつらは僕を笑ったことを後悔するだろう。
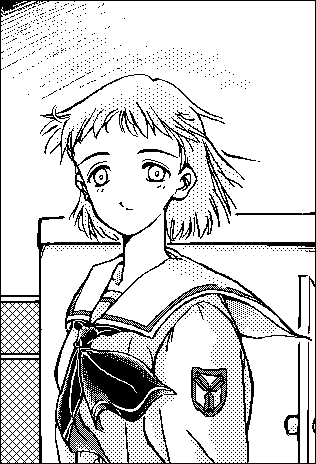
「ホントにそう?」
頭の中での僕の独り言に突然語り掛けられて、僕はびくっとした。
知らず知らず僕は考えながらしゃべっていたのだろうか、僕の考え/妄想を。
「みんな分かってくれるかな、本当の長瀬君を」
女の子の声だ。
僕は聞いたことがある、この声を。
振り向くと、いつのまにかそこには一人の少女が立っていた。月島瑠璃子、去年僕と同じクラスにいた子だ。
そう、僕は瑠璃子さんを知っている。クラスメイト、というだけではなく。
繊細で触れると壊れてしまいそうな瑠璃子さんを、僕はずっと見ていた、あこがれを込めて。でも、そのあまりの透明さに、僕は話し掛けることすら出来なかった。
そして違うクラスに別れてしまい、もう話し掛けるチャンスも無くなってしまったと思っていた。でもそんな僕を瑠璃子さんは覚えていてくれた。
そして今、直接話し掛けてくれている。
でも、今僕の前にいる瑠璃子さんは僕が知っていた瑠璃子さんと違う。
瑠璃子さんは僕に話しかけているけど、視線は宙をふらふらとし、目の焦点は合っていない。そして、、表情がとても幼く感じる。
「そう?」
「?!」
はっと気が付いた。やはり僕はしゃべってなどいない。頭の中で考えているだけだ。だのに瑠璃子さんには僕の心の中の声が聞こえているのだ。
「電波、だよ」
「電波?」
「そう、電波。さっきからずっと長瀬ちゃんは電波を出しているんだよ。だから聞こえちゃうの、長瀬ちゃんのココロの声が」
電波?
電波だって? テレビやラジオみたいな?
それが僕の心の声を“放送”しているとでもいうのだろうか?
「ちょっと違う。聞きたいって思う人にしか聞こえないの。怒っている人の声が聞きたい、って思えばそういう人の電波がきこえちゃうし、、」
それまで宙をさまよっていた視線が、すっと僕に向けられた。吸い込まれてしまいそうな色をした瞳に見つめられ、僕は思わず目を伏せてしまった。
「寂しい電波が聞きたいって思うと、聞こえてきちゃうの。長瀬ちゃんの電波が」
瑠璃子さんの目が何かを語るように僕を見つめた。
「寂しい? 僕が?」
「そう、とっても」
屋上を冷たい風が吹き抜ける、そんな感じがした。
「ずっと、長瀬ちゃんの電波が届いてた。長瀬ちゃんすごい才能があるよ、電波の」
僕に“電波”の才能があるだって?一体瑠璃子さんは何を言ってるのだろう?僕にはまったく理解することが出来なかった。そんな僕の心のなかの声を聞いてか聞かずか、瑠璃子さんは僕を見続けたまま語り続けた。
「ずっとずっと、長瀬ちゃん、自分にはチカラがあるって思っていたよね。他の人にはない、優れた力が」
「あの、その、、」
「そう、長瀬ちゃんには凄いチカラがある。ただそのチカラに気付いてないだけ」
「………」
「早く気付いて。そうすれば、、」
「そうすれば?」
僕の問いに瑠璃子さんは答えず、あいまいな微笑みを僕に向けるだけだった。
それから、僕が屋上に上る理由が変わった。
今まで僕は、街にひしめく愚かな人々を見下ろすために屋上に上ってきた。
でも、あの透明な視線に見つめられた時から、僕は囚われてしまったのだろうか。
何に?
屋上に上がれば瑠璃子さんに会えるから、僕は屋上に上がるようになった。
瑠璃子さんの云う力が欲しいからだろうか? 僕の確信している、僕の中にある他の奴等を圧倒する力を、瑠璃子さんなら僕の中から外へと引き出してくれる、そんな気がするからだろうか。
それともただ単に、瑠璃子さんに会いたいからなんだろうか。
いや違う!
僕のこの気持ちはそんな気持ちじゃない。それじゃ、愛だの恋だの云っていちゃついてる、あの愚かな輩とおんなじじゃないか。違う、僕は瑠璃子さんのことをそんな気持ちでは見ていない。
そう、僕は瑠璃子さんだけがこの学校の中で、唯一のくだらなくない人だと感じている。そして、そう、瑠璃子さんのことを、選ばれたこの僕に近しい存在だと感じる……。
階段の扉を開けて屋上へ出ると、フェンスの側に立ち、空に向かって両手を広げている少女がいた。
瑠璃子さんだ。
夕日の中、キラキラと光るものが瑠璃子さんの手から空へと立ち上って行く幻影(イメージ)が見え、僕はぎょっとして目をこすった。
おかしくなったのだろうか、僕は?
瑠璃子さんに声をかけることも出来ず、僕は扉に寄りかかったまましばらく動くことが出来なかった。
「そんなことないよ」
手を天にかざしたまま瑠璃子さんがぽつりとつぶやいた。
「今、長瀬ちゃんに電波が見えたの」
といって瑠璃子さんは僕に微笑みかけた。
でもその目は、僕を見ているようで僕を見てはいなかった。
「…それが瑠璃子さんの電波だっていうの?」
「そう」
と答え、瑠璃子さんは再び空へと顔を向けた。
夕日の中、陶酔するように空に両手をかざし“電波”を宙へ放つ瑠璃子さんの姿は、まるで太古の巫女のようで、、、美しかった。
「瑠璃子さんは何をしているの?」
沈黙に絶えられず僕は瑠璃子さんにたずねた。
瑠璃子さんは手を下ろすと僕の方に振り向いた。
「電波で、天使を呼んでいるの」
「天使?!」
あまりに予想から遠すぎる瑠璃子さんの答えに僕は面食らった。
天使だって? あの羽が生えていて、両性具有で、、神の使い……。
「変ね。長瀬ちゃんのイメージもみんなとおんなじイメージ。
そんな風にしか天使を捉えられない?」
ふっ、と瑠璃子さんが笑った。
『みんなと同じ』という言葉に僕の頭は白くなってしまった。
「違うよ! あんな連中と一緒にしないでよ!」
瑠璃子さんはそんな僕の言葉など聞こえないかの様に一人、ささやくように語りだした。
「天使はとても強い電波のカタマリなの。
今まで天使は何度もこの次元の地球にレティクル座からやってきたわ。そして電波をみんなに降り注いでくれたの。その暖かい電波を、みんなはそれぞれのイメージで捉えるわ。昔の人は湧き出す電波の奔流を翼に喩えたの」
崇高なものをたたえるかのように『天使』について語る瑠璃子さんを見ると、僕の心はなぜか苛立った。
「天使はなんで地球になんて来るの? わざわざ」
苛ついた僕の問いに瑠璃子さんは至福の微笑みで答えた。
「みんなをシアワセにするために」
「幸せにする?」
「そう。電波で呼びかけ続ければ天使はきっと来てくれるわ。レティクル座まで届くくらい強い電波を送れば、きっと天使は私たちのことを思い出してくれる。そして、天使が来ればその強い電波でみんなを幸せにしてくれるわ。戦いも、いがみ合いも、妬みも、ひがみも、悲しい心も、限りない憎しみも、みんな電波が消してくれるの」
いつもの瑠璃子さんとは思えぬほど熱っぽく語り、陶器のように白い瑠璃子さんの頬が紅潮してきた。
「私、ずっと探してきた。
電波に気付いてくれる人を。強い電波をもっている人を」
そして僕の右手を両の手のひらで包みこみ、“初めて”僕に語り掛けてきた。
「長瀬ちゃん、電波に気付いて。そしてレティクル座の天使にメッセージを一緒に送って、、」
瑠璃子さんの熱い吐息を感じながら、瑠璃子さんへの酸っぱい気持ちにひたりながら、僕は胸をきゅぅっと締め付けられるような痛みを感じるのだった。
「私の電波だけじゃ、弱すぎるの。天使の電波と共振しないの、、、、」
瑠璃子さんの話を聞いて、僕はすべてが分かったような気がした。
瑠璃子さんの心に電波だの天使だの怪しげな言葉を埋め込んだのは、瑠璃子さんの兄、月島拓也だ。
月島拓也、前生徒会長、品行優良な好青年。教師たちの覚えもめでたく、、、
しかし僕は知っている。
周りの生徒からの尊敬のまなざしをあびながら、奇麗な仮面の下で奴は自分以外のすべてを侮蔑し、自分こそが唯一正しい存在だと信じている。
何故なら、奴は僕と同じ目をしているから、、、
教師に従順に従い、後輩から慕われている奴は教師を軽蔑し、後輩たちを石ころほどにも感じていない。
そんな奴が僕は吐気が出るほど嫌いだった。とてもあの瑠璃子さんの兄とは思えない。
でも、そんな月島拓也はある日、突然学校に来なくなった。表向きは転校したことになっているが、精神病院に入院したのだということは、全校生徒が知っていることだ。
そう、月島拓也は『天使を呼ぶ』という意味不明の言葉をわめき散らし、家族によって強制的に遠くの精神病院に送られてしまったのだ。
多分、月島拓也は瑠璃子さんもその怪しげな『電波』と『天使』の世界に引き込んでしまったのだ。あの、人形のように純真だった瑠璃子さんの真っ白な心に自分勝手な妄想を埋め込んでしまったのだ。
そして、月島拓也がいなくなった今もなお、瑠璃子さんは『天使』を呼び続けている。
月島拓也の、兄のために。
月島拓也は、田舎の精神病院の一室に閉じ込められている今尚、瑠璃子さんの心を捉えて離さない。そして瑠璃子さんは世界でたった一人、月島拓也を信じているのだ。
そのことを思うだけで僕の心はどす黒く燃え立つ。
瑠璃子さんの心を、お前なんかが捉えて離さないなんて、許せない。
「死ね、死ね、死ね、死ね、死ね!
瑠璃子さんから明るい笑顔を奪い去って自分勝手な妄想の犠牲にしてしまった月島拓也!
お前なんかのた打ち回って汚泥にまみれて死んでしまえ!」
死ね、死ね、死ね、死ね、死ね!死ね、死ね、死ね、死ね、死ね!
シネ、シネ、シネ、シネ、シネ、シネ、シネ、シネ、シネ、シネ!
僕はそれから数日、瑠璃子さんに会うことが出来なかった。
毎日、放課後屋上に上ってもそこには瑠璃子さんはいなかった。
『天使』とかいうレティクル座から来た宇宙人が瑠璃子さんを連れ去ってしまったのだろうか、というたわいもない妄想が僕を苦しめた。
だとするなら、レティクル座の天使も許すことは出来ない、、、
ある日の休憩時間に僕の耳に“月島さん”という言葉が入ってきた。女の子達の会話だ。
「かわいそうね、結局家族は誰も付き添ってくれなかったの?」
「妹さんだけは見取ってあげたらしいわよ、ほら月島瑠璃子さん」
「最近、ちょっと変になっちゃったあの子?」
「そう。ずっと付きっ切りで看病するんで、学校休んでたらしいわよ」
一体何の話をしているんだ?
月島拓也がどうしたっていうんだ?
そして瑠璃子さんが?
取り乱した僕は女の子達の会話に割って入った。
「ちょ、ちょっと、月島拓也さんがどうしたんだって?」
普段誰とも話さず、一人クラスの輪から外れている僕が話し掛けてきたことに女の子達は、当惑しているようだった。
「月島さんね、入院先の病院で突然お亡くなりになったんですって」
「!?」
「2、3日くらい前から突然苦しみだして、、、とっても大変だったみたいよ」
僕はあまりのとっぴな、いや、あまりに予定調和的な事件の推移に呆然とした。
「それで瑠璃子さんはずっと学校に来ていなかったんだ.....」
「え?」
予想外の僕の呟きの内容に女の子は驚いたようだった。
月島拓也が死んだ?
僕が願ったようにのた打ち回り、汚泥にまみれて死んだのだろうか……多分そうだろう。僕には確信があった。
その日の放課後、僕は屋上に行った。
予想通りそこには瑠璃子さんがいた。
心なしか、瑠璃子さんがやつれているように感じた。
「長瀬ちゃん、電波に気付いたのね」
瑠璃子さんは悲しげにそうつぶやいた。
僕は何も答えられずにいた。
あれが電波だというなら、僕は電波に気付いたことになるのだろうか。瑠璃子さんの云う暖かいチカラをもつ電波とは程遠いものだが、、、
「そう、あなたは電波に気付いた。
でもそれはとても悲しい電波。そんな電波に気付いて欲しくはなかった」
僕は瑠璃子さんの目を見ることが出来なかった。
違うんだ、瑠璃子さん。僕は君のために、君のためを思って、、、
「そういう心が悲しい電波を呼ぶの。そして世界に悲しい心を降り積もらせるの。
ねたみ、そねみ、にくしみ、いかり」
「ちがうんだ! 僕はそんなつもりじゃ、、」
僕は叫んだ。
力の無い叫び。
いや、僕はこういう力をもともと望んでいたんだ。その結果が、これなんだ。
瑠璃子さんは僕を哀れむように見つめ続けた。
僕はそんな瑠璃子さんに語り掛ける言葉を持たなかった。
「天使はもう、ここに来れない」
そう言うと瑠璃子さんは立ち去った。
屋上には僕一人だけ残された。
「あーっ! 長瀬君こんなところにいたの!」
僕の後ろから聞き覚えのある声がした。
「こんなところでサボっていたのね、週番の仕事!
結局今週は私一人でやったのよ! もう!」
女の子の声を聞きながら、不意に僕は涙をこぼした。
それまでこらえていたつもりはなかったが、塞き止められていたものが溢れ出すようにどんどんと涙があふれてきた。
「あ、あの、長瀬君、、」
戸惑う女の子を気に止めること無く、僕は一生分の涙を流した。
その後、瑠璃子さんの姿は学校から消えた。
生徒の間には、UFOを信奉する新興宗教に入って利用されて捨てられた、とか、兄と同じように精神病院に閉じ込められたとか云う噂が流れたが、しばらくすれば瑠璃子さんの存在を誰も思い出すことはなくなった。
瑠璃子さんのその後の行方は誰も知らない。