物音を立てないように気を付けながら身支度を整え、他に起きてくる様子のないことを確認して、台所へ向かう。
台所には薄く朝日が差し込んでいた。
手慣れた様子でエプロンを身に付け、流し台の前に立つ梓。
大きく息を吸って、胸いっぱいに新鮮な空気を送り込む。
いつもなら、このあと柏木家の朝食の用意が始まるのだが。
「食事の用意の前に、ちょいちょいっと片付けちゃいましょうかねぇ。
・・・よしよし、ちゃんと冷えてるな」
冷凍庫の扉を開け、中からなにかをとりだす。
「さて、クーラーボックスはこれでよし、っと。
あとはこれを勝手口から出しておいて、出がけに持っていく。
うーん、我ながらナイスアイデア。
待ってろよ、耕一」
梓が勝手口のドアを開けようとした、その時。
「梓お姉ちゃん、おはよう。今日はいつもより早いんだね」
「うわっ、初音!!」
まだ目を覚ましたばかりなのであろう。ピンとはねたくせっ毛がいつもより多い。
「ふわぁぁ・・・いま、着替えてきてお手伝いするね」
「あっ、あぁ・・・ま、まだ早いから!!
もももももう少しゆっくりしてていい・・・そ、そう、いいよ、初音」
持っていたクーラボックスを慌てて脇に置いてぎこちない笑みを浮かべる梓。
あたふたと勝手口から離れ、ガスコンロ方へ歩いてゆこうとする。
こころなしか、頬が上気している。
「どうしたの? 梓お姉ちゃん?」
初音が心配そうに近付く。
「・・・なんか具合、悪そうだよ。
御飯の用意、あっためるだけなら初音がやるから、休んでた方が・・・」
「なな、なんでもないよ。
ほほほほほら、『早起きは三本の徳利』っていうし、耕一は風邪ひいて寝込んでるし、たまたま早く目が覚めただけだし。
朝は早いと気持ちがいいなぁ・・・なんて、ね、ね」
初音はますます心配そうな顔になった。
まっすぐ見つめる初音の瞳。
その瞳が潤んでいるのに気がついて、ハッとする梓。
まずいっ、と思ったときにはすでに手遅れだった。
「あのね・・・あのね・・・
昨日の電話の耕一お兄ちゃんの声、とっても苦しそうだったの。
もしかして風邪なんかじゃなくて、もっともっと重い病気だったらどうしようって・・・
そう思ったら・・・あんまりよく眠れなくって・・・
そしたら梓お姉ちゃんも具合悪くって・・・ぐすっ・・・」
華奢なその身体が震えていたのは、朝の肌寒さのせいではない。
梓はもうこれ以上、隠し事ができないことを悟った。
「・・・もう、初音は心配症なんだから」
ぎゅっと抱きしめ、優しく髪をなでる。
かすかに冷蔵庫のモーター音が聞こえていた。
「いいかい。あたしはこの通りピンピンしてる。
どっかの不摂生野郎と違って、こっちは毎日規則正しい生活をしているからね。
とはいえ・・・」
梓はここで恥ずかしそうにぷいっと横を向いた。
「ま、まぁ、初音も心配していることだし、あたしもほんのちょびっとは心配だから・・・」
初音の表情がぱぁっと明るくなる。
「耕一お兄ちゃんのお見舞いに行くの!?」
「あ、ああ。でも初音は学校があるから、今日はあたしが行ってくるよ」
「だって、梓お姉ちゃんだって学校・・・」
そういいかけて、流し台の脇に置かれたクーラーボックスと、冷蔵庫の前に置かれた紙袋からのぞく果物の山に気づく初音。
ほんの、ほかの人から見れば全くわからないくらいの一瞬。
少し淋しげな笑顔。
しかし、それはすぐにいつもの明るい笑顔に戻る。
「あのね。
戸棚の奥に、この間の桃缶がまだ残ってると思うから、持っていってあげて欲しいの」
「そうだね。あいつ、むかしっから桃缶好きだからなぁ」
梓は相づちを打ちながら、
初音の表情の翳りの意味を痛いほど噛み締めていた。
少しだけ涙に濡れたパジャマの袖を気にしながら、
初音がくるりと回れ右をする。
「あ、ああ。・・・あ、あのね、初音。
実はこのことはみんなには内緒に・・・」
梓がそう言いかけると、
「耕一お兄ちゃんに、おいしいものたくさん食べてもらって早く元気になってほしいから・・・
梓お姉ちゃん、お願いね」
振り向いた初音の笑顔。
それから、ちょっとばつが悪そうにもじもじしながら
「あとね。
えっとね・・・『早起きは三文の得』・・・だと思うよ」
ほとんど聞き取れないくらいの小さな声。
ぱたぱたとスリッパを鳴らして、初音は台所から出ていった。
「えっ?・・・あ、はは・・・」
ぽりぽりと鼻の頭を掻く梓。
「持つべきものは、ほんっとよくできた妹、だな。
・・・サンキュ、初音。
おまえの分までしっかり看病してくるからな」
梓はエプロンの紐をもう一度結び直した。
おっと、味噌汁の味付けあじつけ・・・ここでタケコメ味噌をば」
専業主婦顔負けの手際のよさで朝食の用意を進めていく梓。
白い湯気と、いい匂いが台所にたちこめる。
「梓姉さん、おはよう」
制服姿の楓が台所に顔をのぞかせた。
きれいに切り揃えられた黒髪と、透き通るような白い肌。
「お、楓。おはよーさん」
「・・・今日も、いい匂い・・・」
この一言は、梓にとってその日の朝食の出来栄えを占う重要な台詞となっている。
柏木家の中で一番味に敏感なのは、他ならぬ楓なのだ。
いつもと変わらぬ答えにほっとしながら
「すぐ出来るから、もうちょっと待っててね」
「えぇ・・・でも、なんだか今日の梓姉さん・・・?」
盛り付けをしていた梓の手が、はたと止まる。
楓が敏感なのは味だけではなかった。
梓自身は極めて自然に振る舞っているつもりなのだが、体がそのままの姿勢で硬直してしまっている。顔を上げようとすると、ぎっぎぎっ、という音が聞こえたような気がした。
「梓姉さん」
じっと見つめる楓の瞳。全てを見通すかのような、深く、澄んだ瞳。
二人の間を沈黙が流れる。
ややあって。
「・・・ううん、なんでもない」
軽くかぶりを振りながら、静かに楓が微笑んだ。
さらさらと黒髪がゆれる。
「そ、そう・・・なんでもない、か」
ふうっと大きく息を吐く梓。
「梓お姉ちゃん、居間の方、用意できたから・・・あっ、楓お姉ちゃん。おはよう」
お盆を抱えた初音が、ぱたぱたと駆けてきた。
「お、おぅ。さんきゅー、初音。ところで千鶴姉は?」
これ以上この雰囲気のままでいるのはまずい、と踏んだ梓が半ば無理矢理話を初音に振る。
「千鶴お姉ちゃんなら、今起きてきたとこだよ。
・・・で、でも・・・あのね。
千鶴お姉ちゃん、昨日、遅くまで起きてたみたいで・・・ほんとに起きたばっかりみたいなの。
・・・それでね・・・わたし・・・」
初音の声はだんだん小さくなっていき、最後の方の台詞はほとんど聞き取ることさえできない。
梓と楓は思わず顔を見合わせた。
「千鶴姉さん、今日は朝から経営会議だっていってたような・・・」
「うっ、こんな日に限って、これかよ」
思いっきり苦虫を噛み潰したような表情の梓。
心配そうに見つめる楓と初音。
台所には、ぴーんと張り詰めた空気が漂っていた。
・・・あたしは千鶴姉のところへ行ってくる」
凛とした梓の声。ぐっと握り締めたこぶしが、固い決意を示す。
よく見ると小刻みに震えているが。
「梓姉さん、くれぐれも気をつけて」
「千鶴お姉ちゃん、さっき洗面所のところにいたから・・・きっとまだ部屋には戻ってないと思うの」
「分かった。
・・・なぁに、大丈夫だって。ちょっと行って千鶴姉の目、覚ましてくるだけだから」
「この前のときみたいに、無理だけは絶対しないでね」
「私もときどき朝、つらいから、気持ちは分かるんだけど・・・」
「おぅ、まかせとき。姉ちゃん、明日はホームランだ」
不安げに見つめる二組の瞳に梓なりに精いっぱいの安心を映しながら。
梓は台所をあとにした。
しばらくして
「梓姉さん、前にもああいって出てった・・・」
思い出したように、楓がつぶやいた。
板の間がきしむ。
途中でスリッパを履き忘れてきたことに気付いたが、かまわず進んでゆく梓。
「そ、そうさ。心配することなんてないんだ。
起き抜けの千鶴姉なんて、はっきりいってゾウガメ以下のトロさなんだから。
そんなの、あたしの手にかかれば・・・」
徐々に足音が小さくなっていく。
「・・・前のときはたまたま油断して、寝間着を着たままシャワーを浴びようとしていた千鶴姉を止めようと、羽交い締めにしたのがいけなかったんだ。
おかげでまともに肘鉄をくらって・・・あのときは死ぬかと思ったぜ。
千鶴姉の一撃はやたらめったらきついからなぁ。
えぇっと、その前は確か・・・」
梓は足音を忍ばせながら渡り廊下を進んでいった。
向こうからゆっくりした足取りで歩いてくる千鶴の姿が目に入る。
ちょっと大きめの紺のナイトガウンとおそろいのナイトキャップ。少しだけ乱れたガウンの裾の下に見えるのは愛用の白のロングスリップか。
ブラとショーツ付けた方が体型のためにいいのに、と思いながら梓は声をかけようとした。
「あっ!!」
千鶴がふらふらっとバランスを崩して、縁側から庭へと足を踏み外そうとしている。
ダッシュする梓。
陸上部で鍛えたカモシカのような脚としなやかな身体が、普通では考えられない程のスピードを生む。
目にも止まらぬ速さで渡り廊下を駆け抜け、千鶴に手を伸ばす。
「耕一さん・・・むにゃむにゃ・・・」
その声を聞いたとき、梓は千鶴の目が閉じられたままであることに気付いた。
梓の右手が肩に触れようとしたそのとき、千鶴の目が見開かれた。
燃える紅の瞳。
その瞬間、時間が止まったような気がした。
千鶴が梓の右腕を掴む。
身体をひねりながら投げをうつと同時にその肘を極め、折ろうとする。
自分の意識というよりは本能的に感じたのであろう。梓は自ら投げられる方向へと身体を流すとともに、極められていた肘を振りほどく。
次の瞬間、梓の身体は大きく宙を舞っていた。
びゅっ。
梓が本来落ちるはずだった空間を千鶴の廻し蹴りがなぎはらう。
「・・・なかなかの身のこなし。
だが、このリズエルに触れることなど、疾風のエディフェルを以ってしてもあたわぬ・・・って、
え? えっ?」
梓がこの台詞を聞いたのは、庭の潅木の茂みの中であった。
ごそごそと茂みから這い出す梓。
あちこちに引っ掻き傷があるものの、それほど大きなダメージを受けた様子はない。
もし、まともにくらっていたら間違いなく病院へ、下手をしたらそのままあの世へ直行であろう。
「・・・?」
きょとんとした顔であたりを見回す千鶴。
ナイトキャップの先についたぼんぼんがゆっくりと弧を描き、そして止まった。
「あら、梓。おはよう。
・・・でもなんでそんなところにいるの?」
がくっ、と梓が前に突っ伏すのが見えた。
「まぁ・・・どうしたのかしら?」
梓からの反応はない。
千鶴はふと、自分の服装に気が付いた。
「やだ・・・私ったら寝間着のままなんて。
着替えてきますから、梓はちゃんと靴下を履き替えるんですよ」
ゆっくりと遠ざかる千鶴のスリッパの音が聞こえた。
左頬にぺたっと貼られたバンドエイド。
「・・・だいたい、眠ったまま起きてくるっていうのが間違ってるんだ。
あたしが気が付かなければ今ごろ・・・」
初音がかいがいしく手当てをしている間も梓の小言は続いていた。
くどくどくどくど。
先刻から千鶴は小さくなりっぱなしである。
湯気の立つ朝食を前にして、少し困ったような表情の楓と初音。
「でも、千鶴姉さんが夜更かしするなんて・・・?」
楓が素直な疑問を口にする。
「そうなのよ。
私もね、明日は経営会議だから早く眠らないと、って思ったんだけど、耕一さんのことを考えると私が看病に行ってあげないと・・・でも明日の会議は絶対出るように、っていわれてるし・・・でもでも耕一さんに早くよくなって欲しいし・・・」
ちょっと照れたようにもじもじとする千鶴。
白いブラウスの胸の前で、つんつんと人差し指を突き合わせる仕草がなんともいえない。
一瞬の硬直の後。
「・・・おぅ。冷めないうちに食べちまおう」
「いただきます」
「千鶴お姉ちゃん、お先にいただきまーす」
「・・・??・・・もうっ!!」
千鶴がぷうっと頬を膨らませた。
黙々と食べる楓の方を見て、梓は満足そうにうなずく。
茶碗を置き、味噌汁の碗を取ろうとした楓がその視線に気付いて、恥ずかしそうに目を伏せる。
「・・・おいしい」
「うん。とってもおいしいよね、楓お姉ちゃん」
初音が相槌を打つ。
「そ、そうかな?」
えへへ、と照れ笑いを浮かべる梓。
「わたしも早く梓お姉ちゃんみたいにおいしいお料理、たくさん作れるようになりたいな。
耕一お兄ちゃんが喜んでくれるような・・・」
小さくつぶやく初音。
口にした台詞に気付いて、ぽっと頬を染める。
「大丈夫。初音は筋がいいから、すぐに作れるようになるさ。
・・・うん。あたしが保証する」
梓はもう一度、大きくうなずいた。
梓は二人の妹の間にいる千鶴に目を向けた。
ぼんやりして、あまり食が進んでいない。なにやら考え事をしているようだ。
「千鶴姉。ダイエットなんて、これ以上やったら、ただでさえない胸がぺったんこになっちまうから、止めといた方が・・・」
「梓、なにかいった?」
千鶴が梓の方を向いて、にっこりと微笑む。
背後にゆらゆらと立ち上る鬼気が見えるような気がした。
「な、なんでもないです」
反射的に答えてしまう梓。
「・・・だからね。
私、今日、耕一さんのところへ行ってこようと思うの」
ようやく決心した、という千鶴の表情。
どうやら食事の間ずっと考えていたらしい。
「えっ?」「・・・」「!!」
三人の箸が一斉に止まった。
だんっ。
梓がちゃぶ台を叩いて立ち上がった。
「耕一のとこにはあたしがっ!!・・・うぐぐぐっ」
慌てて自分で自分の口をふさぐ。
「あ、あの・・・その・・・えーと。
そ、そうだ。今日は大事な会議があるんだろ?
だだっだったらそいつに出なくちゃいけないじゃないか。
べ、別に、なにも見舞いに行く必要なんて・・・うっ。
ない・・・そ、そうさ。ないんだってば。
ここここ耕一のことだから、ゆっくり休んでうまいものでも食べれば、す、すぐによくなるって。な、な、な」
火がついたように真っ赤になりながら必死の説得を試みる梓。
背中を冷や汗が滝のように流れ落ちる。
「でも・・・一人暮らしっていったらおいしいものなんて食べられないし・・・
やっぱりここはわたしが行ってお料理してあげ・・・え?」
はっしと千鶴の右袖をつかんだ楓が、ふるふると首を横に振っていた。
わたしもここは梓お姉ちゃん・・・じゃなかった、
えーと、えーと・・・
今日は千鶴お姉ちゃん、お仕事に行った方がいいと思うの・・・わたしもほんとはお見舞い、行きたいんだけど・・・」
最初は照れ笑いにも似た表情だったが、最後に小さくつぶやくと、目を伏せてしまう初音。
沈黙が居間を包む。
「あなた達・・・」
千鶴はゆっくり三人へと視線を巡らし、梓のところで止めると、小さく息を吐いた。
「・・・お座りなさい、梓。
わかりました。
あなた達がそこまでいうなんて、余程のことですからね」
初音の表情が明るさを取り戻す。
楓はつかんでいた手を放し、ほっと安堵の息を漏らした。
「余程のことなのは千鶴姉の料理だよ。
あんなもの食べさせられたら、治るものも治らなくなっちまう」
腰を下ろした梓がぼそっとつぶやく。
先刻までの狼狽から回復し、いつもの調子に戻っている。
「な、なんですって!?」
「なんですってもかんですってもないやいっ。
まさかこの前の『魔の七草粥事件』を忘れたとは言わせないからねっ!」
「あ、あれはほんとに・・・」
「たまたま調子が悪くって・・・てへっ、とか、言うつもりじゃないでしょうねっ!!」
「うっ・・・」
にぎやかな姉達のやり取りを見ながら、楓と初音は笑顔でうなずき合い、朝食の続きを取りはじめた。
初音。あなたそろそろ行かないといけないんじゃなくて?」
掛け時計を見上げた千鶴が、一時休戦、とばかりに初音に声をかける。
「あっ、・・・うん」
味噌汁を飲み終えて、初音は碗の横に箸をそろえた。
「ごちそうさまでした」
「・・・ごちそうさま」
楓も箸を置いて立ち上がった。
かなり前に食べ終わってから、ずっと姉達の様子を見守っていたらしい。
初音が食器をお盆に乗せようとすると、
「私がやるから・・・早く支度なさい」
「ありがとう、楓お姉ちゃん」
ぱたぱたと部屋へと急ぐ初音。
「おっと、あたしも?
・・・んっ・・・んぐぐぐ、ぐるじぃ・・・」
「もうっ、そんなに急いで食べるからですよ」
「梓姉さん、お茶」
「・・・ふぅ。助かったよ、楓。
さんきゅーモンテスキュー、なんちって」
そこには淡々と後片付けを続ける楓と、知らん顔で朝食を食べ終えようとしている千鶴の姿があった。
梓が手早く食器を洗い、楓がそれを拭いて食器棚にしまっていく。
きゅっきゅ、きゅっ。
布巾と食器の奏でる軽やかなリズム。
「相変わらず、楓は食器拭くの早いよなぁ。
・・・こう、ふきふきって」
梓が感心したようにつぶやく。
「あ・・・」
何かを思い出したのか、手を止めてうつむく楓。
頬がほんのり桜色に染まっている。
「梓姉さん・・・」
顔を上げ、自分を見つめる瞳に、梓は思わずどきっとしてしまう。
「もう・・・からかわないで・・・」
消え入りそうな声。
「あ・・・いや・・・その、からかったわけじゃなくってさ。
・・・はいよ、これで終わりだから」
楓が少し恥ずかしそうに皿を受け取る。
水の流れる音が止み、パタン、と食器棚の扉の閉まる音が聞こえた。
「初音。ハンカチとちり紙は持った?」
「はーい・・・ってもう、千鶴お姉ちゃん。わたしいつまでも子供じゃないもん」
靴の紐を結んだ初音が弾むように立ち上がる。
トレードマークのくせっ毛がぴょこん、と大きく跳ねた。
千鶴の後ろにいる梓と楓に気付くと、
「梓お姉ちゃん、楓お姉ちゃん。今朝は・・・ごめんなさい」
どうやら朝食の後片付けができなかったことを気にしているらしい。
「うぅん・・・」
ゆっくりとかぶりを振り、優しく微笑む楓。
「いいってことよ。・・・今朝はいろいろあったからね」
梓の台詞に千鶴がちらっと後ろを振り返る。
「別に千鶴姉だけのことをいったんじゃないんだけどなぁ」
「わ、わたしは、そんな・・・」
「夜更かしなんてしてるからだよ、もう。
寝不足は身体とお肌の大敵なんだからねー。千鶴姉もそろそろ気を付けないと・・・」
うっしっし、と意地悪そうに笑う梓。
「もー、お姉ちゃん達ったら・・・」
苦笑しながら初音が仲裁に入った。
「いってらっしゃい。車に気を付けるんですよ」
千鶴の優しい声に、
「はーい」
元気いっぱいで答える初音。くるりと向きを変え、戸に手をかける。
がらがらがらっ。
「はっ、初音。・・・きょ、今日の夕飯なんだけど・・・」
慌てたように梓が声をかける。
初音は背を向けたまま立ち止まり、やがてこくん、と小さくうなずいた。
「・・・梓お姉ちゃん・・・お願いね」
祈りにも似たかすかなつぶやき。
「はーい。わかってるから」
振り向いた初音は笑顔で答えると、少し急ぐようにぱたぱたと陽射しの中に駆けていく。
「梓姉さん・・・」
楓が心配そうに梓を見つめていた。
千鶴が怪訝そうに尋ねる。
梓の表情がこわばった。
「あ、その・・・いや・・・あの・・・今日はちょ、ちょっと遅くなるかもしれないから・・・」
千鶴と楓のまなざしにどぎまぎしながら、かろうじてこれだけを口にする。
「また陸上部の後輩の指導?
・・・面倒見がいいのはとってもいいことだけど、あなたは受験生なんですからね」
「へっ?」
一瞬きょとんとしてしまう梓。
「・・・そっ、そうそう後輩の指導。
そーなんだよ。かおりのやつったらさぁ。もううるさくってうるさくって」
ほっと胸をなで下ろしながら心の中で千鶴の早合点に感謝する。
「今度の三者面談のこともあるし・・・まぁ、あなたのことだからそんなに心配してないけど」
「それでね、梓。この間の進路の話のことなんだけど・・・」
半ば唐突に千鶴が話を切り出した。
梓の台詞に、楓が寂しそうな表情を浮かべる。
「でも・・・」
「あれはあたしが決めたことだから。あたしは・・・」
そこまで言いかけると、ふっと視線を下に落とす梓。
頬が熱くなっているのが分かる。
顔を上げようとすると、傍らの置き時計が目に入った。
「・・・って、そんなことしてる場合じゃなかった。
もうこんな時間だよ。さっさと用意して耕・・・じゃなかった、学校行かなきゃ。
・・・千鶴姉、話は帰ったら聞くから」
「あ、梓っ!」
慌ただしく奥へと消える梓を呆然と見送る二人。
「もう・・・しょうがないわねぇ」
やれやれ、といった感じで苦笑する千鶴。
「梓姉さん・・・やっぱり・・・」
楓がぽつりとつぶやく。
「そうね・・・今日中に帰ってくるのは無理でしょうから。
帰ってきたら話をしっかり聞いてもらいましょ」
千鶴はにっこりと微笑むと、楓の肩をぽんぽん、と軽く叩いて居間に戻っていった。
「千鶴姉さん・・・」
びりびりと痺れるような肩の感覚に、楓はしばらくそこに立ちすくんだままだった。
レースのカーテン越しに差し込む暖かな陽射しが、室内に柔らかな濃淡を描く。
「・・・とりあえず忘れ物はないよな」
部屋を見渡す梓。
準備のほとんどは昨日のうちに済ませてあった。
ドアのそばには大き目のスポーツバック。三年間、陸上部の合宿や遠征で世話になったお気に入りの品である。
「あとはこいつと勝手口の荷物を持って出ればOKっと。
・・・おっと、いけない、いけない。忘れるところだったよ」
勉強机の方に目を向けると、静かに歩み寄る。
机の上にはいつも使っている通学用の鞄。中の教科書やノートは今日の科目とは若干異なっている。
「今日の授業の必要なところは後で写させてもらうとして。
・・・電車の中とか、結構時間はあるだろうから。
千鶴姉達にもああ言っちまった手前、やれることはやっていかないとな」
苦笑いを浮かべながら鞄に手を伸ばそうとして、ふいにその場にしゃがみ込む。
梓はゆっくりと机の一番下の引き出しに手をかけた。
手前側には何冊かの日記帳の背表紙。奥側にはおそらく梓のお手製であろう、布の巾着袋がひとつだけ置かれているのが見える。
梓は袋を持ち上げると、口紐を緩めて注意深く中のものを取り出した。
ほとんど履かれていないと思われる一足の靴。
水色のスポーツシューズタイプ。子供用なのか、今の梓が履くにはずいぶんと小さい。
かなり古い物の様だが、手入れが行き届いているため、あまりそれを感じさせない。
よく見ると右に比べて左の靴だけが若干色あせ、なにか尖ったもので引っ掻いたような傷が何個所かあった。
優しく左靴の傷をなでる梓。
-
「・・・あいつはまだ、思い出さないんだよな。
でも、あたしは・・・」
静かに目を閉じる。
静寂が部屋を満たす。
「・・・さてと、行きますカニっと」
梓は丁寧に靴をしまうと立ち上がった。
「よっこらせっと」
スポーツバックを持ち上げると、ひょいと肩に担ぐ。
ふと、この他にも持っていく荷物のことを考えて、思わず苦笑してしまう。
「問題は千鶴姉だよな。
見送りに出られると勝手口に行けないからなぁ」
梓はドアノブを回すと、廊下に出た。
「・・・ここは、この手しかないか」
ばたんっ。
勢いよくドアを閉めると、大きく息を吸い込む。
「・・・ふぅ。よしっ」
さも忙しそうに早足で歩き出そうとして、身体の向きを変えると、
「うわわっ。ち、千鶴姉!」
「だ、だっていつもは居間で茶でものののの飲みながら、役に立たない痩身体操とかやっ・・・」
千鶴の眉がぴくっと動いたように見えた。
「梓、それはどういうことかしら?」
「は、はいぃ」
すくみ上がる梓。蛇に睨まれた蛙とはこのことをいうのだろうか。
長年の習慣が梓の身体を無条件に反応させてしまう。
千鶴は小さく息をつくと肩をすくめた。
「まぁ、いいわ。
・・・わたしも今日は早くお迎えの方が来るから、そろそろ支度をしないと、と思って」
梓が大きく安堵の息を漏らす。
「それじゃ、梓。車には気を付けるんですよ」
梓の横を通り過ぎ、奥の自分の部屋へと歩いてゆく千鶴。
「・・・あっ、それと」
突然なにかを思い出したように千鶴が振り向いた。
今にもスキップでもしそうな勢いで渡り廊下の方へ歩いていこうとしていた梓が、恐る恐る後ろを向いた。
「な、なな、なんだい、千鶴姉・・・?」
引きつった笑い。
見方によっては今にも泣き出しそうにも見える。
「遅くなるようだったら連絡するんですよ」
いつもと変わらぬ微笑みを浮かべながら優しく呼びかける千鶴。
「お、おぅ。わ、分かってる」
短く答えながら、梓は胸が痛むのを感じていた。
「じゃ、行ってきます」
「ええ、いってらっしゃい」
いつも通りのやりとり。
ゆっくりと歩き出した梓が曲がり角から姿を消す直前、
「・・・これくらいは気を利かせてあげなくちゃね」
後ろで小さくつぶやく声が聞こえたような気がした。
「楓・・・?」
そっと障子を開けると、仏壇の前には身支度を済ませた楓が座っていた。
目を閉じて座する姿は、黒髪と肌の白さも手伝ってか、端正な日本人形を思い起こさせる。
思わず見とれてしまう梓。
「あ・・・梓姉さん」
視線に気付いた楓が顔を上げた。
さらさらと流れる黒髪。
「あ、あはは・・・いやその。
あたしはこれで行くから。あとはよろしくね、楓」
照れ笑いを浮かべながら梓が言葉を返す。
こくん、とうなずく楓。
その瞳が潤んでいるように見えたのは、梓の気のせいだったのだろうか。
「じゃ、行ってき・・・」
「あの・・・」
立ち上がった楓が思いつめた表情で梓を見つめていた。
何気なく答えた梓は、次の瞬間はっと息を飲んだ。
楓の両の拳が強く握られ、小刻みに震えている。
うつむいて必死に言葉を紡ぎだそうとしている姿を見て、何を言わんとしているのかが直感的に理解できたような気がした。
「わ、私も・・・私も・・・」
その先は言葉にならない。
頬をつたう涙の雫。
「うっ・・・うっ・・・うわぁぁぁん・・・」
押し殺していた感情が堰を切ったように一気に流れ出す。
駆け寄る楓を抱き止める梓。
手から鞄が落ち、スポーツバックが小さく揺れた。
「・・・楓」
優しく楓を抱きしめる。
その身体はあまりにも華奢で、ちょっと力を込めれば簡単に壊れてしまいそうだった。
楓は梓の胸に顔を埋めながら、
「ほんとは、私も・・・私も、耕一さんのところへ・・・」
「・・・もう、いいから。・・・わかってるから、な」
梓は指で梳くようにゆっくりと楓の髪をなでながら、胸がきりりと痛むのを感じていた。
楓のおさまるのを待って声をかける。
梓の胸にこくん、とうなずく感触が伝わった。
「あたしはこれから、耕一のところへ行こうと思っている。
・・・もう気付いてたみたいだけど、ね」
再び楓が小さくうなずくのが分かった。
「いや、あたしの身勝手だっていうのは分かってるんだ。
楓も初音も・・・そう、千鶴姉だってすっごく心配していて・・・。
初音なんかさ、電話の声がひどくつらそうだったって思わず泣き出しちゃうしさ。
・・・ほんとにただの風邪なのにさ・・・はは・・・」
苦笑しようとしたが、うまく笑えない。
ぽつり。
楓は、頭に小さな雫が落ちたような気がした。
「梓姉さん・・・」
少し身体を引くようにしながら、顔を上げて梓を見つめる楓。
「はは・・・あたし、なにやってんだろ」
梓はごしごしと拳で顔をぬぐう。
頬のバンドエイドが少し剥がれかかっていた。
そうつぶやいたのは楓だった。
「え?・・・楓が謝ることなんてないじゃないか。
むしろ、悪いのはあたしの方で・・・」
梓の台詞にふるふるとかぶりを振る。動きにつれて揺れるおかっぱの髪。
「わたし・・・自分のことしか考えてなくて・・・姉さんを困らせてしまって・・・」
「なにいってんだよっ」
梓が楓の両肩を掴む。
あっ、と小さく声を上げてしまう楓。
「今更こんなこと言えた義理じゃないけど・・・それでも。
悪いのはあたしなんだ。だから・・・」
まっすぐに楓を見つめるまなざし。
その瞳に安心したように、楓は優しく微笑んだ。
「耕一さんのこと、お願いします。・・・みんなの分も」
「楓・・・」
次の瞬間、楓は強く抱きしめられていた。
苦しそうな声に梓が慌てて手を放す。
「ご、ごめん。・・・大丈夫だった?」
心配そうな梓に向かってこくりとうなずく楓。
ほっ、と息をつくと梓は真剣な表情で楓を見つめ、深く頭を下げた。
「ごめん・・・ほんとにごめん」
「・・・そんなことしないで、姉さん。
わたし、梓姉さんなら安心だから・・・耕一さんにお大事に、って伝えてください」
少しはにかんだような微笑み。
「楓・・・あんたってコは・・・」
顔を上げた梓は今にも楓を力一杯抱きしめそうな雰囲気である。
楓はそれを知ってか知らずか、
「今晩にでも電話・・・ください・・・ね」
うつむきながら小さくつぶやく。
こころなしか頬が赤く染まっている。
「あ、ああ。必ず連絡する。約束するよ。
・・・そういえば、さっき千鶴姉にも同じこといわれたっけ」
梓が思い出したように苦笑いを浮かべた。
玄関の戸を開ける。
「じゃぁ、いってくるね」
振り向いた梓は楓に声をかけた。
楓は、顔を洗ってきたらしく前髪の一部がその艶を失っている。注意して見ないと、泣きはらした跡には気付かないであろう。
「いってらっしゃい。
・・・耕一さんによろしく伝えてください」
「OK。みんなの分、しっかり看病してくるよ」
うなずきながらスポーツバックの肩紐を掛け直した。
「そういえば・・・千鶴姉さんは?」
「あぁ、千鶴姉なら今日は早いからって部屋でおめかし中。
なんか早すぎるような気もするけど・・・まぁ、こっちにとっては願ったりかなったり、かな」
いたずらっぽく笑う梓。
不思議そうに見つめる楓の視線に、
「あはは・・・えっと、その・・・勝手口にさ、ちょっとした荷物があって・・・アイスノンとか、あいつが持ってるとはとても思えないし。
ほんとは内緒で出掛けに持って行くつもりだったから、千鶴姉に見送られたりするとまずいかなぁ・・・なんてね」
「梓姉さん・・・やっぱりすごい」
楓が感心したようにつぶやく。
「よ、よせやい」
梓は空いている左手でぽりぽりと鼻の頭を掻いた。
「そう・・・忘れ物しないようにね。
あとは・・・そうそう、『車に気を付けるんですよ』だ」
いつもなら千鶴が言う台詞である。
梓は片目をつむってぺろっ、と舌を出した。
「ええ」
こくりと楓がうなずく。
それから、少し困ったように躊躇しながら、
「・・・でも、あんまり似てない」
「やっぱり?・・・はは、こりゃまいったね」
頭の後ろに手をやって苦笑する梓。気にした様子は全くない。
すぐにそれは笑顔に変わり、楓も微笑みを浮かべる。
笑い合う二人。
「あ、そうだ」
ふいに梓が真面目な表情になる。
「あのさ。千鶴姉にはこのことは内緒にしておいて欲しいんだ。
どうせ今晩には電話できちんと話すつもりなんだけどね」
「はい。・・・でも」
なにかを言いかけて楓はふっと口をつぐんだ。
首をかしげる梓に、
「千鶴姉さん、きっともう・・・ううん、なんでもない」
軽くかぶりを振って静かに微笑む。ふるふると黒髪が揺れる。
「そっか。・・・なんでもない、か」
独り言のようにつぶやく梓。
「それじゃ、あとはお願いね」
「はい。いってらっしゃい、梓姉さん」
楓の言葉を背に受けて敷居をまたぐ。
「いってきまーす!」
がららららっ・・・ぴしゃん。
元気の良い声と戸を閉める音が響く。
楓はすりガラスから梓の影が消えるのを見送りながら、
「・・・千鶴姉さん、きっともう気付いてると思う。
でも、それは梓姉さんも・・・」
目を閉じるとほんの少しだけ寂しそうな表情を浮かべた。
玄関を出た梓は左手の腕時計に目をやると苦笑いを浮かべた。
「さてっと」
門へと続く敷石の列からはずれて家の裏手へと足を向ける。
勝手口へと続く軒下の細い通路は薄暗くひんやりとしていた。
さくっ・・・さくっ。
氷の力によって持ち上げられた地面を踏みながら歩く。
「・・・楓も初音も、なんでこう鋭いんだろ。せっかくの完璧な計画が台無しだよ。
さすがはあたしの妹たち、ってところかな。
ま、超絶鈍感な千鶴姉にだけは気付かれてないみたいだけど」
くくくくっ、と声を殺して笑う梓。
その後でふいに悪寒を感じてぶるっと身を震わせる。
「おーさむさむっ。やっぱ日が当たらないと寒くていけないねぇ。
・・・なんか急に気温が下がったような気がするけど。
まぁ、いっか。さっさと行こ行こっ」
急ぎ足で軒下を抜け、角を曲がって裏庭へと出る。
陽射しが梓の視界を奪う。目をしばたかせながら勝手口の方へ視線を巡らすと、
「な、なんじゃこりゃぁ!?」
勝手口のコンクリートの露台の上には、いくつかの荷物が置かれていた。
アイスノンや氷枕などを入れたクーラーボックスと、果物や缶詰の入った手提げ袋には見覚えがある。
「あたしが置いたのはこれと、これ・・・だよな」
問題は二つの荷物よりもさらに大きい薄青色の風呂敷き包みだった。あちこちに不自然な出っ張りがあり、頂点は固い小目結び。
苦労して結びをほどいた梓は、包みの中身を確認しはじめた。
まず目に付くのは贈答用の細長い桐箱が二つ。焼判を見るまでもなく、中に入っているのは一升瓶であろう。
平べったい新聞包みはその大きさと軽さから、
「・・・湯たんぽ、だろうな。おいおい、この湯沸かしって台所のやつじゃないか。
でもって、こっちのバックの中は・・・」
使い捨てカイロだった。それも、バック一つがすべて。
その奥の買い物袋にはレトルトカレーの箱がぎっしり詰められている。
「く・・・うぷぷっ・・・あはははははは・・・」
思わず笑い出してしまう梓。
もう一つの袋に山と積まれていたカップラーメンのうちの一つが、ころころと足元に転がり落ちてきた。
「わ、わかったからもう・・・あは・・・笑わせないでくれ・・・おかしすぎて・・・涙が・・・」
しゃがみこんだ梓の背中が、小さく震えていた。
梓は風呂敷きを包み直して立ち上がった。
「これで前よりは持ちやすいだろ。
とはいえ、さすがのあたしでもこれだけ持って歩くのは一苦労だな、こりゃ」
当初の予定よりもはるかに多くなった荷物を眺めて苦笑いを浮かべる。
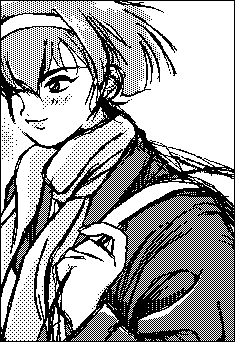 |
「どっこらしょっと」 右肩にスポーツバック、右手に学生鞄と手提げ袋。左肩にクーラーボックス、左手に風呂敷包みをぶら下げる。すべてを合わせればその重さはかなりになっている筈だ。
裏庭にある格子戸をくぐって外に出る。
「うーんっ」
くるりと身体の向きを変え、軽やかに駆け出す。
〜おわり〜
|