− 2 −
雨戸とカーテンの閉め切られた寝室は、机上灯以外の明かりがなく、廊下よりも若干明るい程度でしかなかった。室内灯のスイッチを入れると、柔らかい光が部屋を満たす。
部屋に入った千鶴は、しばらく自分の入ってきたドアを見つめていた。俺は部屋の奥へ歩みを進めると、何気ない素振りで机にある綴りかけの便箋をそっと引き出しにしまい込む。背を向けている千鶴には、どうやら気付かれなかったようだ。ほっと胸をなで下ろしながら、俺は千鶴に声をかけた。
「千鶴・・・」
「・・・はっ、はいっ。ご、ごめんなさい、私ったらぼーっとしちゃって。これだから梓にいつも『すろーりー』とか『亀姉』なんて言われちゃうんですよね」
少し驚いたように、こちらに身体を向ける千鶴。はにかむような笑顔を浮かべて、こつんと軽く自分の頭を叩くと、片目をつむって小さくぺろっと舌を出す。時折見せる彼女の茶目っ気たっぷりの仕草は、美しく成長した今でも変わっていない。というより、それはむしろ現在の彼女の魅力を倍加させているようにさえ思えた。
そう、彼女は美しい。
身内という贔屓目を差し引いても、それは誰の目にも明らかだと思う。
さらさらと流れる黒髪。
白く透き通った肌。
均整の取れた顔立ち。
ともすれば美しすぎる女性は冷たい印象を持たれがちだが、千鶴の微笑みは、見るもの全てに安らぎと親しみを感じさせてくれる。
そういえば、千鶴が三月まで通っていた地元の大学の美人コンテストで、四年連続で優勝したのは、いくら田舎の大学とはいえコンテスト開始以来の快挙だったらしい。もっとも、千鶴自身は恥ずかしがってそのことを家では一切話そうとしなかったが。姉に内緒で大学祭を見に行った梓たちが、嬉しそうに俺に話してくれたのを思い出す。
・
・
・
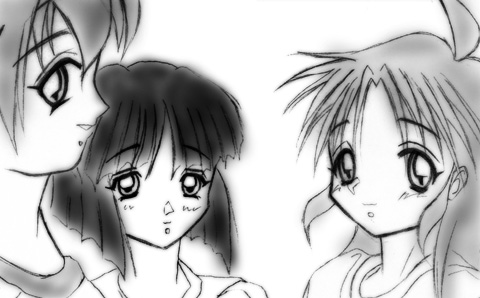
居間に入った俺を待っていたのは、いつもと少し様子の違う夕食の風景だった。
「千鶴はまだ帰ってきていないのか・・・それにしても、鯛の尾頭付きなんて、なにかおめでたいことでもあったのかい?」
豪華な夕食を前にして、どことなく落ち着きのない梓、楓、初音の三人に声をかける。どうやら、三人とも俺に話したいことがあるようだ。その様子を見て、俺はあることを思い出す。
「そういえば、今日はみんなで千鶴の大学の大学祭に行って来たんじゃ・・・」
「美人コンテスト、優勝だったんです。千鶴姉さん・・・しかも四年連続の」
三人の中で、口火を切ったのは楓だった。静かな口調はいつもとあまり変わらないが、その笑顔を見れば彼女の気持ちは手にとるように分かる。
「ほお・・・すごいな。初耳だよ」
素直な感想な口にする。肝心の千鶴がまだ帰ってきていないのは、大方、祝賀会を兼ねた打ち上げにでも付き合っているということなのだろう。
「でしょでしょ。・・・ったく、水くさいよなー。千鶴姉も。そんなこと、ひとっこともあたし達に話してくれないでさ。『せめて最後の年くらいみんなで見に行かないとね』ってことで、こっちが内緒で行ってなけりゃ、みんな知らないままだったんだぜ」
梓が口を尖らせるのも無理はない。だが千鶴の性格を考えると、自分の自慢になるようなことを進んで話すとも思えなかった。
「でもねでもね。すごいんだよ、千鶴お姉ちゃん。なんでも、コンテスト開始以来の快挙なんだって」
すかさず初音がフォローを入れる。姉のことを本当に嬉しそうに話す様子を見ていると、自然と俺の口元にも笑みが浮かぶ。

「千鶴姉のやつ、柄にもなく顔、真っ赤にしちゃってさぁ」
うっしっし、と口に手を当てて意地悪そうに笑う梓。・・・若干素直でないのも一人ほどいるようだ。
「ま、千鶴姉の本性を知ったら、とても投票なんてできなくなると思うけどなぁ」
「あっ・・・」
小さく声を上げた楓が、梓の脇腹をちょんちょんとつつく。だが梓はそれに気付かないのか、俺に向かって自慢の毒舌を披露し続けている。
「なにしろ、料理は全くできない、家事は人並み以下。いつもぼーっとしてるし、胸だってせいぜいあたしと同じくらいだし、そのくせ切れると手加減なく・・・え?」
さすがの梓も、自分の後ろに立ち上る蒼白い冷気の炎を感じたらしい。
「手加減なく・・・どうするのかしら?」
「えっ?」
錆付いたちょうつがいのような、ぎしぎしという音を立てて、梓が首を巡らす。恐る恐る見上げた視線の先には、今日の豪華な夕食の主賓がにこにこしながら梓を見下ろす姿があった。
「はははは・・・は。お、お帰り、千鶴姉・・・」
梓の顔に引きつった笑いが浮かぶ。初音と楓が困ったように俺の方に視線を送るが、こうなってしまっては、俺とてどうこうできるものではない。
俺は苦笑しながら、やれやれといった風に肩をすくめた。
・
・
・
そう、彼女ハ美シイ。
だが俺は、彼女が振り向いた瞬間に見せた一瞬の表情の翳りを見逃すことができなかった。優しい笑顔の裏に潜む哀しみの素顔。もしかしたら、それすらも彼女の美しさを引き立てるための小道具だったのかもしれない。
俺は椅子の背もたれを持って逆向きに回転させながら、千鶴の方を見る。寝室には机に備え付けのこいつ以外、椅子はなかった。
「すまないが、そこのベッドでも使ってくれ」
「はい」
千鶴はうなずくと、抱えていた洋服をベッドの上に置き、ちょこんとその横に腰を掛けた。タイトスカートからすらりと伸びた脚が、ストッキングのせいで薄い光沢を放つ。
ソウ、彼女ハ美シイ。
俺も背もたれに胸を合わせるように身体を預け、椅子に腰を下ろした。千鶴は着ていたジャケットを脱ぐと、自分の横に置く。最初にどの服を選ぶか迷っているらしく、しばらくベッドに視線を落としていたが、やがて一着のワンピースを選ぶと、立ち上がってそれを身体にあてがいながら、俺の方に笑顔を向けた。
「これなんて、どうですか?」
はしゃぐようにくるりと一回転して、ポーズをとる千鶴。艶やかな長い黒髪と白いワンピースの裾が、声のあとを追うようにふわりと弧を描く。
ソウ、カノジョハウツクシイ。
細すぎるくらいの肩。
力を込めて抱きしめれば折れてしまいそうな腰。
はにかむように微笑んで俺を見つめるまなざし。
白磁のような素肌にうすく紅をさした唇。
普段は化粧っ気のほとんどない彼女だが、今晩は違っていた。かすかな香水の匂いを感じる。
たかが俺に洋服選びを頼むだけなのに、ずいぶんめかし込んでるな。
いつもの俺なら、笑いながらそのことを千鶴に告げたであろう。
「・・・おじさま?」
「あ、あぁ・・・いいんじゃないか」
だが実際は、気のないような返事をするのが精一杯だった。その美しさに一瞬我を忘れていた、という方が正しいのかもしれない。
ドクン。
俺の中の何かが、かすかに動いたような気がした。