− 5 −
俺は彼女を強く抱きしめていた。
泣いているあいつ。
泣いている千鶴。
ふいに、先刻のドアをじっと見つめていた千鶴の姿と、振り向きざまに見せた一瞬の表情の翳りとが思い出された。
・・・あのとき、すでに気付いていたのだろうな。
ドアの閉まる音が以前と異なった重みを感じさせるものになっていること。
扉の内側に付けられた鍵や蝶番が新しく、頑丈なものに取り替えられていること。
そして、それらの事実から予想される可能性。
俺の中で、今までの千鶴の行動がそれぞれ明確な理由を持ってひとつに繋がっていく。
妹たちが寝静まった頃を見計らった深夜の来訪。
役に立たないと分かっている服の見立て。
普段はめったにつけない香水の香り。
俺の前にあらわにされた素肌。
全ては千鶴が俺に対して抱いていた、ある疑問を確かめるための行動だった。そして、千鶴の導き出した答は・・・
最悪の結果。
予想通りの結果。
俺が「力を操れないもの」であること。
俺が「滅ぶべき存在」であること。
八年前、兄夫婦、つまり千鶴の両親が命を落とした不可解な事故は、決して事故などではなかった。兄貴は俺と同じ「力を操れないもの」だった。呪われし力にその意識のほとんどを支配され、身も心も恐ろしい怪物へと変貌していく兄貴に対して、義姉さんが差し伸べることのできた唯一の救いの手。愛するがゆえに、それ以上の悲劇を引き起こすまいと自らの命を絶った二人。
だが、それは残された千鶴たち四姉妹にとって、あまりにも残酷な選択だった。
頼む・・・
初音を、楓を、梓を・・・
千鶴を・・・
お願いします・・・
真相を知っているのは、俺とあいつ、そして全てを事前に両親から話されていた千鶴だけだった。
残された姉妹と、柏木の家、伝統、そして、呪われた血。当時、中学生だった千鶴に全てを背負うことは不可能だった。現在でも、それが彼女にとってどれほどの重荷になっているかを、俺は分かっているつもりだ。
だから、俺はここに来た。
息子である耕一と、妻であるあいつを残して。
・
・
・
その夜、俺は耕一が寝付いたことを確かめてから、あいつに自分の決心を告げた。
「・・・すまない」
「そんな・・・顔を上げてくださいな、あなた」
深く頭を下げた俺に向かって、あいつは微笑みながらそう言った。俺の言葉が、あいつと耕一にとってどういう意味を持つのかを理解した上で、それでもあいつは俺に微笑みかけていた。
俺のやろうとしていることは、本当に正しいことなのだろうか?
「義兄さんと義姉さんが、命を懸けて守ろうとしたあの子たち・・・千鶴ちゃん、梓ちゃん、楓ちゃん、初音ちゃんを、呪われた運命から守ることができるのは・・・あの子たちの笑顔をもう一度取り戻すことができるのは、あなたしかいないのですから」
「だが・・・」
「それが、あなたの・・・あなたの選んだ道なのでしょう?」
あいつは俺を責めるどころか、励まそうとさえしていた。そうすることが、あたかも当然であるかのように、努めて明るく振る舞おうとするあいつ。だが、途中から涙声になったあいつの言葉をこれ以上聞くことは、俺には耐えられなかった。
「私と耕一のことは心配なさらないで下さい。これでも私はあなたの・・・柏木賢治の妻ですから」
その瞬間、俺はあいつを強く抱きしめていた。その細い肩を抱くのは、美しい黒髪を撫でるのは、これが最後だと知りながら、それでも、今だけはその手を離したくなかった。
・
・
・
「これは離婚じゃないんですから。私も、耕一も、柏木の性を捨てません」
今でもはっきりと思い出すことができる、あの朝のあいつの台詞。
「いってらっしゃい」
「父さん、いってらっしゃいっ」
まるで毎日会社に出かける俺を見送るかのように、明るく微笑むあいつ。その隣で、まだなにも知らない耕一が元気よく俺に声をかける。
「ああ、いってくる」
俺は最低限の荷物だけをまとめた鞄を手に、二人の方を向いていた。背からさす朝日のせいで、俺の顔が二人にはっきりと見られないであろうことを、俺は心から感謝した。
あいつも、できる限りの笑顔で答えたつもりだったのだと思う。だが、必死にこらえようとしても、次々と涙の雫が頬をつたい落ちていく。
「・・・どうしたの? 母さん」
耕一が不思議そうな顔をしてあいつを見つめる。あいつはぼろぼろと涙を流しながら、それでも俺に手を振り続けていた。
あいつは俺を恨むだろうか。
あの子は俺を許してくれるだろうか。
俺はあのとき、あいつの涙を拭ってやることができなかった。俺は、自らその資格を放棄したのだから。
 ・
・
・
・
それきり、俺があいつに会うことはなかった。・・・そう、あいつが生きている間は。物言わぬ骸を前にして言葉を失った俺に、耕一の視線が冷たく突き刺さる。
やはり、憎んでいるのだろうな。
自嘲するように口元を歪め、俺は耕一に話し掛けた。
「お前さえよければ、柏木の家で・・・一緒に暮らさないか」
「・・・・・・」
耕一は無言のままだった。その目には、俺に対する激しい非難の色があった。
「いいえ。俺は父さ・・・いや、貴方の世話になるつもりはありませんから」
「・・・そうか」
耕一は俺の申し出を断り、一人で暮らしていくことを告げた。俺も、それは仕方のないことだと思った。ただ、えらく他人行儀で感情のこもっていない耕一の物言いに、八年という歳月の長さと、あのときの自分の選択に対する責任の重さを感じざるをえなかった。
その後、耕一とは顔を合わせていない。
・
・
・
あのときのあいつの泣き顔が、今の千鶴にだぶって見えた。
あのときの耕一の言葉が、今も俺の胸に突き刺さっていた。
・・・もう、いくら謝ったところで、許される筈もないのだろうが。
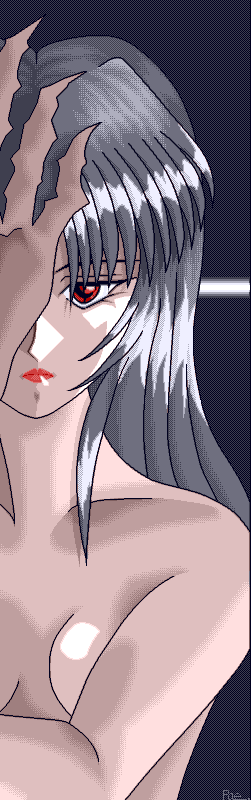
今や膨れ上がった欲望は、熱い激流と化して俺の細胞の一つ一つにまで行き渡り、それらを急激に活性化させていた。俺の身体は、燃えるような高揚感と、本来の姿を取り戻すことの喜びに打ち震える。
そんな中でも、俺の意識は不思議なほどはっきりしていた。なぜかは分からないが、俺の中のもう一つの意識である「奴」が俺の意識を封じている力に隙が生じていた。それは、誰かが俺に与えてくれた最後のチャンスだったのかもしれない。
・・・そろそろ終わりにしようじゃないか。
俺は千鶴から手を放し、数歩後ろへ下がる。
これ以上、こんな奴を自由にしておくわけにはいかないからな。
その間にも、異形のモノへの変貌は進んでいく。人間という弱く、小さく、もろいだけの生物にはない、大きく、鋭い爪と牙。そして背中を丸めてすら天井に届きそうなほどの体躯。服が爆ぜ、軋んだ床がみしみしと音を立てる。千鶴を見下ろす真紅の瞳には、おそらく歓喜と狂気の光が溢れていることだろう。心の奥底から絶え間なく吹き出す殺戮と蹂躪の欲求が、俺の身を焦がす。だが、その欲求に身をゆだねるわけにはいかなかった。
今度こそ、負けられないっ。
千鶴は金縛りに遭ったように立ち竦んだままだった。その目には、もう二度と見たくなかった八年前と同じ悪夢が映っている。だが千鶴は、俺から目を逸らそうとはしなかった。その瞳に浮かんでいたのは、恐怖でも絶望でもなかった。
温かい輝き。
ひとつの固い決意。
優しく微笑んで目を細める千鶴。流れ落ちる一筋の涙。
願いは・・・願いは、叶えられないものなのですか?
みんな笑顔で「おはよう」って言える朝がくるのを願うことすら、私には許されないのですか?
本当は、鶴来屋なんていらないのに。
柏木の血なんて忌まわしいだけなのにっ。
俺の心に流れ込んでくる千鶴の心。これも鬼の力の影響なのだろうか。俺は、千鶴の心から発せられた最後の言葉を感じ取った。
おじさま・・・あなたを・・・
次の瞬間、俺の方を向いた千鶴の顔からは全ての感情が失われていた。
あなたを・・・殺します。
その瞳は、鮮やかな血の色に染まっていた。